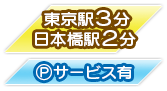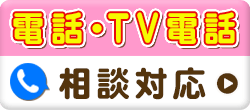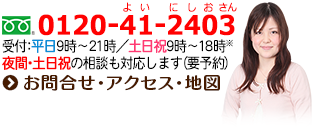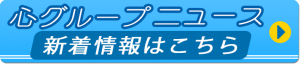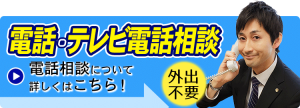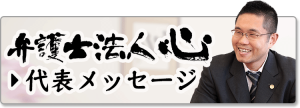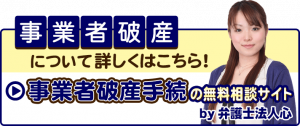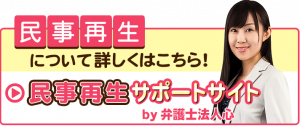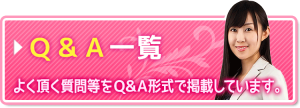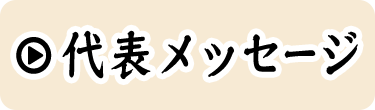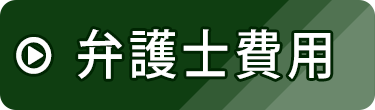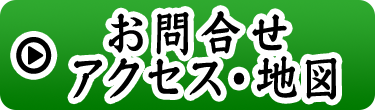渋谷にお住まいで会社破産をお考えの方へ


1 渋谷から当法人へのアクセス
当法人は、都内に複数の事務所を構えております。
渋谷からであれば、東京駅から徒歩3分の事務所や、池袋から徒歩3分の事務所、銀座一丁目駅から徒歩4分の事務所等がお越しいただきやすいかと思います。
どの事務所であっても、会社の債務問題を得意としている弁護士がしっかりとお話をお伺いいたしますので、安心してご相談にお越しください。
2 会社破産とは
会社破産とは、簡単に言えば「会社の財産を全てお金に換えて、債権者に分配した後で法人を消滅させるための手続」です。
そもそも「法人」とは、法律の中でのみ人格(法人格)を認められている存在であり、「自然人」である人間とは異なります。
そして消滅とは、文字通り「消えてなくなること」です。
当たり前かもしれませんが、この「消滅」こそが、自然人と大きく違う部分となります。
例えば自然人である私達が破産(自己破産)しても、その存在が消滅するわけではありません。
自然人は破産後も継続して存在しているため、法律で認められた権利や義務はいくつかの例外を除いて存続します。
しかし法人が破産すると、その存在がなくなってしまい、それとともに法人の権利も義務も消えてしまうのです。
3 破産をすると会社の財産や資産はどうなる?
会社破産すると、会社の財産を「清算」することになります。
清算とは、会社の財産や権利等を「すべて」お金に換えて、債権者や株主などに配当することを言います。
つまり会社破産の後は、会社の財産も資産も全てなくなってしまうのです。
ちなみに、会社清算型の手続きとしては、「破産手続」以外にも「清算手続」というものがあります。
この「清算手続」には、主に以下のような種類があります。
・通常清算:資産が超過しているときに行う
・任意清算:合名会社や合資会社が解散する場合に行う
・特別清算:債務が超過しているときに行うが、債権者の協力が必要
債務が超過しており、かつ債権者の協力も得られない場合は、裁判所に申し立てて「破産手続」を行って会社を消滅させます。
4 手続の方法・流れ
会社破産をするときに、「とにかく会社の財産を売却して債権者に配当すればいいんだな!」と思う人がいるかもしれませんが、それは間違いです。
会社破産は裁判所を通して行う手続であり、裁判所が選任した「破産管財人」という専門の人が財産を管理し、調査し、売却を行い、そして債権者や株主などに配当を行います。
そのため、手続の前に勝手に会社の財産を売却すると、不当な財産処分となり、後で問題になってしまうおそれがあります。
一般的に、会社破産は以下のような流れで行われます。
⑴ 破産の準備
裁判所に申し立てる前に、必要書類や資料を揃えます。
この段階が既に大変なので、弁護士に依頼することが一般的です。
弁護士は各種書類や資料を作成してくれたり、申立てにあたってどの様な書類を集める必要があるのか教えてくれたりします。
また、弁護士に依頼すると、銀行や貸金業者等の債権者は弁護士を通じてでないと債務者とやり取りできなくなります。
このため、個人債権者等を除き督促から一旦は解放されます。
⑵ 裁判所に申し立て
実際に裁判所へ破産の申し立てを行います。
弁護士がいれば、弁護士が裁判所に行く等して手続きしてくれるので、申立ての段階では、破産する企業の代表者は裁判所まで足を運ばなくても大丈夫です。
⑶ 破産審尋
裁判所の運用次第ですが、通常は「破産審尋」と呼ばれる面談が裁判所で行われます。
裁判官と破産申立人のほか、破産申立人が依頼した弁護士、そして場合によっては破産管財人となる予定の弁護士が面談に参加します。
したがって、この段階では、破産する企業の代表者は裁判所まで足を運ぶ必要があります。
面談でわからないことがあったら、依頼した弁護士にサポートしてもらえるでしょう。
⑷ 破産手続開始決定
面談の結果、破産の要件を満たしていると裁判所が判断すれば、「破産手続開始決定」が行われます。
破産管財人が正式に選任されて、破産手続が本格的にスタートします。
なお、自己破産では「同時廃止」という破産管財人が選任されない方式が採用されることもありますが、会社破産の場合は必ず破産管財人が選任されます。
⑸ 財産の調査や売却
破産管財人が会社の資産や負債を調べます。
経営者に不正行為がないかの調査も行われるため、素直かつ誠実に応じてください。
不正行為があると手続に支障が出る可能性があるので、前もって自分で依頼した弁護士に「自分は不正行為をしていないか」「もし不正行為をしていた場合は、どう対処すればいいか」などを確認しておきましょう。
調査が終わると、破産管財人が会社の財産を売却して現金化し、債権者へ配当するための資金を保管します。
⑹ 債権者集会
破産管財人が調査の進捗や配当の見通しなどを債権者に対して報告するのが「債権者集会」です。
裁判所で開かれます。
この段階でも、破産する企業の代表者は裁判所まで足を運ぶ必要があります。
⑺ 配当
破産管財人が各債権者に配当を行います。
⑻ 法人の消滅
配当が終わると破産手続が終了し、法人が消滅します。
5 会社破産をするメリット
会社破産の手続きに着手をすると、経営者も従業員も仕事を失ってしまいます。
取引先に至っては債権を回収できなくなったり品物を納品してもらえなくなったりするため、ときに大きな損害を受けるでしょう。
それらのデメリットを受けてまで会社破産をするメリットはどこにあるのでしょうか?
⑴ 債務から解放される
最も大きいメリットはこれでしょう。
会社破産により、債務の取り立てから解放されますし、債務を返済するために四苦八苦する生活からも解放されます。
債務に苦しむ生活から脱して再スタートを切れますし、うまくすれば再起も図れるかもしれません。
⑵ 早期の対処で従業員や取引先への迷惑を少なくできる
債務超過のまま営業していると、取引先に支払いができなくなりますし、従業員への給料も遅配したり、支払うことができなくなってしまう可能性があります。
そのままでは取引先も従業員も不安で仕方ありません。
再建の見通しが立たないのであれば、早期に会社破産に踏み切った方が、周囲にかける迷惑が少なくなります。
ある程度の残余財産がある場合、会社破産して会社を消滅させることで、取引先は最低限の弁済を受けられる可能性がありますし、新しい商売の相手を確保するために切り替えて行動できます。
従業員にしても再就職に動きやすくなりますし、しばらくの間なら失業保険を受けることで凌げるかもしれません。
⑶ 保証人以外は会社の債務を引き継がなくて済む
経営者の方にとっての不安の1つが、「会社破産した後、自分はどうなってしまうのだろう」ではないでしょうか?
例えば自然人が死亡すると、亡くなった人の遺族などが故人の財産や負債を承継します。
これと同じように、「法人が消滅した後は、責任者である自分が法人の義務や負債を引き継がなければならないのではないか?」と考える人がいても無理はありません。
しかし法人と自然人はあくまでも別人格であるため、先に出てきた合名会社や合資会社のように、元々社員が無限責任を負う形態の会社以外の場合、法人が破産しても経営者に影響は及びません。
このため経営者は、消滅した法人の債務を引き継がなくても済むのです。
ただし、中小企業などは経営者が会社の債務を個人保証していることが多いでしょう。
そういった場合は経営者も自己破産することで、保証債務の支払義務から免れることができます。
6 会社破産のことは弁護士へ相談を
会社破産の手続は複雑です。
裁判所へ申し立てる前の資料作りでさえ、日常業務と並行しながら行うのは難しいでしょう。
また、自分でなんらかの対策を行おうとして、財産を処分したり財産を移動したりすると、それらが後で会社破産の手続に悪影響を及ぼすこともあります。
債務超過で経営の継続が困難になった場合は、まだ傷の浅いうちに、できるだけ早く弁護士に相談してください。
会社破産に関する様々な手続を代行してくれますし、破産手続に至る前段階から「問題なく破産できそうか」「トラブルになりそうな事柄がないか」などをチェックしてくれます。
場合によっては、何か他の再建策を教えてくれるかもしれません。
会社の経営に行き詰まったら、当法人の弁護士にお早めにご相談ください。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します(要予約)
所在地
〒103-0028東京都中央区
八重洲1-5-9
八重洲加藤ビルデイング6F(旧表記:八重洲アメレックスビル6
0120-41-2403